マックス「心のホッチキス・ストーリー」第14回の受賞作品を決定
~大賞は、母の日に兄弟で贈る折り紙の花が、家族の幸せを彩ることを描いた作品に~ マックス株式会社は、第14回
マックス「心のホッチキス・ストーリー」と題し、“あなたが今、心にホッチキスしたいこと”をテーマに、ショートストーリーを募集しました。
2023年8月1日(火)から2023年9月29日(金)までの募集期間で、全国から13,406件の応募がありました。
厳正な選考の結果、受賞作品を以下の通り決定しましたのでご報告いたします。
なお、受賞作品は、当社WEBサイト上( https://www.max-ltd.co.jp/about/cocoro_story/
でも公開しています。 https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/72040/31/72040-31-d3c9b45cb696077efd2bc04ba1fbeabe-2800x1600.jpg?format=jpeg&auto=webp&quality=85%2C65&width=1950&fit=bounds)
* 応募作品の傾向
2023年は、新型コロナウイルス感染症に関する各種制限の緩和により、以前の日常生活に少しずつ戻りはじめ、様々なイベントが再開するようになった一方、世界の紛争を目の当たりにして、いつも通りの生活を送ることの意味や、平和について考えた一年となりました。
応募作品では、いつも傍にいる家族の大切さに気づいた作品やコロナ禍で大変だった時に先生の真心を感じた作品など、日常生活を支えてくれている周囲の方への感謝を表現する内容が多く寄せられました。
「マックス・心のホッチキス大賞」には、毎年母の日に弟と折り紙で作った花にメッセージを書いてプレゼントし、母が“しあわせ花瓶”と題した花瓶に飾るエピソードで、普段は照れくさくて直接言えない感謝の気持ちが溢れた作品を選定しました。
「マックス・U-18大賞」には、夏休みに祖父と過ごす楽しさと、帰る時の寂しさを素直な気持ちで綴った作品など3点を選びました。「マックス賞」には、石炭産業の衰退に伴い寂れた故郷を嫌って離れ、移り住んだ町の盆踊りの会場で、炭坑節に合わせ楽しく踊っている人々を目にし、故郷を誇らしく感じた経験を綴った作品など5点が受賞しました。
引き続き、マックス「心のホッチキス・ストーリー」を通じて、みなさまが大切な瞬間を振り返り、日常生活の中にある小さな幸せに気付く手助けになれれば幸いです。
* 受賞作品
マックス・心のホッチキス大賞
<宮崎県> 蛯原 暖 さん (13歳)
「今年はこれにしようか」
母の日が近付くと、ぼくは弟と一緒に折り紙の本に夢中になる。なぜなら、折り紙で作った花を母にプレゼントしたいから。
このプレゼントは、幼稚園生の頃から続けている。はじめはチューリップからのスタートだった。それから、さくら、カーネーション、ひまわり、あさがおなど毎年かぶらない花をぼくと弟で1輪ずつ作っている。また、その折り紙の花には、毎年、母への感謝の気持ちを書くことにしている。
母の日、母は「しあわせ花瓶」と題した花瓶にぼくたちが作った花をうれしそうに飾る。10回目の今年、いよいよ「しあわせ花瓶」はぼくと弟の花でいっぱいになっていた。玄関に飾っているため、学校から帰ってきて真っ先に目に入る。ぼくもとても幸せな気持ちになる。

今年中学生になったぼくは、アヤメの花を折ることにした。毎日、朝夕駅まで送迎してくれること、毎日お弁当を作ってくれることなど、母への感謝の気持ちを手紙に表すことができた。直接伝えるのは何だか照れくさく言えずにいたことを、折り紙を通して伝えることができてとてもすっきりした。
お母さん、いつもありがとう。
これからもよろしくお願いします。
来年は、どんな花にしようかな。ぼくの楽しみの1つである。
マックス・U-18大賞 高校生の部
<神奈川県> みより さん (15歳)
「もしもし、おばあちゃん!」一人暮らしをしている祖母の安否確認の為に始めた電話。毎日お互いにたわいのない話をするだけだが、祖母は最後に決まって「忙しいのにいつもありがとう。明るい声を聞くと元気が出るわ。」と言ってくれる。それが嬉しく、照れくさくてなかなか言えなかった感謝の言葉を私も自然に口に出来るようになった。遠慮がないので時々意見が合わず気を悪くすることもあるが、次の日には必ずまた電話をかけたくなるから不思議だ。

先日、祖母が入院することになり、ほんの数日、話をすることが出来なかっただけで、心にポッカリと穴が空いたような寂しさを感じた。今までは電話をしてあげているつもりだった。でも実際には逆で、経験豊かな祖母から日々様々なことを教わり、支えられていたのは私の方であったのだと気付いた。
学校から帰るとすぐに私は今日も祖母に電話をする。「もしもし、今日はねえ。」
マックス・U-18大賞 中学生の部
<千葉県> 加藤 春華 さん (12歳)
学校の門の前にいる警備員さん、私の心の友達だ。小学校一年生からの付き合いなので、今年で7年目だ。
朝、学校に着いた時、帰り、学校から出る時、いつも声を掛けてくれる。
「今日は暑いねぇ、気をつけてね。」
「元気?」
「一日がんばってね。」
他愛のない話だが、私はこの時間がいつも楽しみだ。

学校で嫌な事があった日や、先生におこられた日、疲れた日でも警備員さんと話をするとほっとして、気持ちが明るくなる。
ある時、警備員さんの一人が、新しく入った警備員さんに私を紹介してくれた事があった。
その時、私のことを
「私の親友です。」
と言ってくれた。この時、私のことを親友と思ってくれているんだなぁと思ってとてもうれしかった。
「私も警備員さんのこと親友と思っているよ。」
と言いたいところだが、恥ずかしくて、まだ言えていない。
マックス・U-18大賞 小学生以下の部
<東京都> たまピ さん (7歳)
私のじぃじは、ちばにすんでいるからなかなか会えない。夏休み前にパパに
「夏休みにちばいこうか。」
と言われてワクワク楽しみにしていた。
じぃじの家では毎ばん私が、じぃじにビールを入れるかかりだ。ビールを入れてあげた時、ジュワーと音がするといつも
「あァー、たまはやっぱりうまいわー。」
と言われる。おいしそうにビールをのむじぃじを見ると私も、うれしくなる。

しょうぎをしたこと。すごろくをしたこと。パズルをしたこと。アンデルセン公えんのプールであそんでくれたこと。たこさん公えんのすべりだいであそんでくれたこと。でん車公えんのまわりを自てん車でまわったこと。じぃじとすることは全ぶ楽しかった。
かえる時、さびしくてないた。そのよる、さびしくなってなきながらねた。はずかしいのでママとパパに
「どうしたの?」
ときかれても
「なんでもない。」
と答えた。
じぃじのことが、大好き。またいっしょにしょうぎしようね。
マックス賞
・京都府 つじ ゆうこ さん (42歳)
・茨城県 はるちょこ さん (33歳)
・神奈川県 なつむ さん (16歳)
・東京都 我らサレジアン さん (14歳)
・大阪府 田代 直樹 さん (10歳)
<京都府> つじ ゆうこ さん (42歳)
故郷が嫌いだった。かつて日本一の炭鉱があった町。しかし閉山後、人口は半分ほどに減り、繁華街は寂れてゴーストタウンのようになった。衰退する故郷を離れ、私は昔から憧れていた京都へと移住した。

京都で生活を始めて数年後の夏。鴨川沿いを歩いていると、聞き覚えのある歌が風に乗って運ばれてきた。導かれるまま辿り着いたのは、近くにある高校。校庭では盆踊りが行われており、そこで流れていたのは『炭坑節』だった。炭鉱のイメージとはかけ離れた雅な町で聞く、故郷の「三池炭鉱」の名前。集まっていた京都の人達はみな、その歌詞に合わせて楽しそうに踊っていた。故郷の炭鉱は全て閉山した。しかし『炭坑節』の歌詞の中で、地元どころか遠く離れた地でもその存在は生き続け、多くの人を笑顔にしていた。それほどまでに素晴らしい故郷の誇りを、疎ましく思ってしまった自分を恥ずかしく思った。
祭りの本部席に行き、自分が「三池炭鉱」の町の出身だと告げると、役員の方々は再び『炭坑節』を流してくれた。しかもヘビーローテーションで。京都の町に何度も響く炭鉱の名前を聞きながら、私は誇らしげな気持ちで踊りの輪に加わった。
<茨城県> はるちょこ さん (33歳)
私の両親は、私が小さい時から共働きだったため、夕飯はみんなで祖母の家で食べるのが習慣だった。料理上手だった祖母は、育ち盛りで食べ盛りの私たちの胃袋を満足させてくれるような夕飯をいつもテーブルいっぱいに並べてくれた。祖父は厳しい人で、「ご飯は、一汁一菜でいいんだ」とよく言っていたけれど、食べ盛りの私達にとって、メインが肉も魚も卵もあるなんて、本当にご馳走だった。

終活という言葉をメディアでよく聞くようになりだした頃、冗談まじりで祖母に「ばぁちゃんは、棺に何入れて欲しい?」と聞いたことがあった。
祖母は、「まな板かねぇ」と答えた。私は、こんなに年季が入ったものをと思ったが、数年前に祖母が亡くなったときは、小さくしたまな板を棺にいれた。それから、私が結婚して娘が産まれ、朝昼晩とご飯を作るようになった時、いかに祖母が一生懸命ご飯を作ってくれていたか、いかに料理が上手だったかがよく分かった。
祖母にとってあのまな板は、祖母の人生そのものだったんだなと、今度は私が娘のために台所に立っている。
<神奈川県> なつむ さん (16歳)
私が小学生の頃、夜ご飯の前に父さんと喧嘩をした。夜ご飯が嫌いなメニューだったため不機嫌な態度をとった私に父さんは、「もうお前に食べさせるものはない。」と言って、私のお皿を取り上げた。私はムキになって何も食べずに自分の部屋に籠った。それから一時間くらいベッドの上でぼーっとしていた。夜ご飯を食べていないので正直お腹が空いた。でも今リビングに戻ったら父さんがいるし、なにより自分のプライドが許さなかった。お腹空いたなーと天井を眺めていると、母さんがおぼんを持って部屋に入ってきた。
おぼんの上には大きなおにぎりが二つのっていた。「なにこれ?」と母さんに聞くと「父さんがなつの為に握ったから食べな。父さん、なつがお腹空いてるんじゃないかって心配しながらおにぎり握ってたよ。」と少し笑いながら言った。お腹が空いていた私は、

十分もかからずその大きなおにぎりを二つ平らげた。具は何も入っていないただの塩おむすびなのに何よりも美味しく感じた。お皿を片付けるついでにでも父さんに謝ろうと思いリビングに行った。しかし、リビングに父さんはいなかった。母さんに父さんの居場所を聞くと「もうとっくに寝たよ。」と言われた。寝室に行って、ドアを開けると父さんはもう横になっていた。謝るのは明日でいいやと思いもう一度リビングに戻ろうとすると父さんは私に背を向けながら「お腹いっぱいになったかー?」と聞いてきた。
私は「美味しかったよ」と一言だけ言ってドアを閉めた。その後すぐに父さんはいびきをかいて寝ていた。「ごめんなさい。」とは言えなかったけど仲直りには充分すぎる父さんのおにぎりだった。あの時よりも美味しいおにぎりを私はまだ知らない。
<東京都> 我らサレジアン さん (14歳)
「しりとりしよう」これが父と私の魔法の呪文である。父は無口で無愛想、おまけに私は母っ子であるためほとんど父と会話する機会がなかった。なんとも気まずい関係である。ある日、家へ帰宅すると家の前に父の赤い車が

停まっていた。本来なら父はまだ仕事中のはずであるのに。「母さんが倒れた」父のいつもより強張った表情を見て私はすぐさま車に乗りこんだ。息を拒みたくなるほどの沈黙が車内に流れこみ、私はおもわず泣き出しそうになった。「しりとりしよう」父の優しいあの声は今でも耳に残っている。きっとバックミラー越しに私の表情が見えたのであろう。ハンドルを握りしめた父の手は小刻みにふるえていた。私は元気よくうなずく。「うん!しりとりしよう」父の不器用ながらの優しさを私は知った。幸い母は軽い熱中症であった。「早く行くぞ」「はーい」私は父の赤い車に乗りこむ。今日はドライブの日なのだ。私達は魔法の呪文をとなえる「しりとりしよ」。
<大阪府> 田代 直樹 さん (10歳)
四年前の冬、ぼくの家に新品のランドセルが届いた。箱を開けるとすぐに背負ってみた。少し大きいけどよくにあっている。春になったらぼくはこれを背負って小学校に行くんだ。そう考えるとすごくワクワクした。友達はできるかな、先生はやさしいかな…楽しい気持ちがふくらんでいく。しかし思ってもみなかった事がおこった。新型コロナウイルス感染症がもういをふるった。ようち園の最後の一か月はすべて休園。町からは人のすがたは消え、家族みんなで買い物に行く事さえできなくなった。当然のように入学式は中止。4月からの登校もなくなり、動画配信のじゅ業が行われる事が決まった。悲しい気持ち、がっかりした気持ち、でもだれかが悪いわけでもない仕方ない気持ち。ぼくの心はもやもやしたままだった。
本当だったら新品のランドセルを背負って小学校に行くはずだった入学式の日。学校から動画が送られてきた。駅から学校までの道のり。桜満開の校門をくぐり、先生たちの大かんげいの拍手にむかえられて体育館に入る。

担任の先生に一人ずつ名前をよばれてお祝いの言葉を聞く。まるでその場に参加しているような気持ちになった。まだ会った事のない先生たちの真心が伝わってきた。今日からぼくは小学生になったんだと感じた。オンラインじゅ業、分散登校三年間にわたるマスク生活の後、今ようやく日常がもどってきた。友達と顔をあわせて話せる事、みんなで集まって勉強したり遊んだり笑ったりできる事、当たり前の日常がどれほど貴重なものか、ぼくたちはだれよりも知っている。だからこそ当たり前の一日一日を大切にすごそうと思う。
きっとぼくは忘れない。非常事態の中でも当たり前のようにぼくたちをかんげいし入学式を開さいしてくれた先生たちの真心を。そして入学式の日に感じた晴ればれとした決意を。
イラスト:北村人

1981年東京生まれ。東海大学教養学部卒業。神戸芸術工科大学 非常勤講師。
毎日新聞日曜版「新・心のサプリ」、星野源「そして生活はつづく」などのイラストや「おひさまでたよ」、「カシャッ!」などの絵本制作も手掛けるイラストレーター。





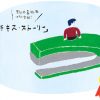


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません